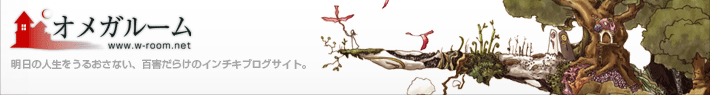(解説)濡れ縁に腰掛け、未亡人は暮れなずむ風景を虚ろに眺めていた。遠く、遙に消えた影を探すように、彼女は鈍い光を持った目で、ただ一点を眺めていた。
(解説)濡れ縁に腰掛け、未亡人は暮れなずむ風景を虚ろに眺めていた。遠く、遙に消えた影を探すように、彼女は鈍い光を持った目で、ただ一点を眺めていた。
「花火、しませんか?」
突然彼女は言った。僕の返事を待たずに、広縁に向かい、線香花火を手に戻ってきた。
ライターで蝋燭に火をともしてあげると、彼女はいとおしそうに線香花火を束から一本抜き取り、火をつけた。
小さな光が、生まれたての闇を穏やかに照らした。つかの間の静寂が、線香花火の灯を一層華やかにした。
刹那、玉となった花火は、地面に落ちた。
沈黙が流れた、静寂とは違う、どこか沈んだ空気を含んだ闇が庭に覆っていた。
「花火って、いつか消えちゃうから、キレイでいられるんですよね・・・」
どれくらい時間がたっただろう、彼女はぽつりと言った。
永久に動き出さない時間を背負わされた、彼女の痛みが嫌でも僕に伝わってきた。それは夏の終わりの闇だった。
そしてやっとフォトショットで絵を描くのに慣れてきた・・・。
« 全国未亡人連合-画廊・My bony- | メイン | 全国未亡人連合-画廊・雨- »
全国未亡人連合-画廊・花火-
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.w-room.net/mt/mt-tb.cgi/48
2010年04月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最近のコメント
最近のエントリー
リンク
検索
Powered by
Movable Type 3.34
Movable Type 3.34