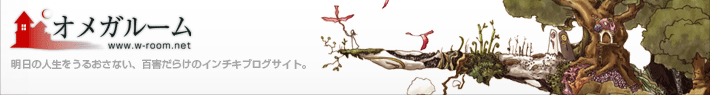(解説)未亡人の体が冷たいのは、雨のせいだろうか。僕は小刻みに震える小さな肩を、壊れないように慎重に、包んだ。
(解説)未亡人の体が冷たいのは、雨のせいだろうか。僕は小刻みに震える小さな肩を、壊れないように慎重に、包んだ。
秋雨が掠める秋の夜は、静かな広がりを見せ、僕等を囲んでいた。
濡れたシャツに取りすがる彼女の手は、あまりに弱弱しく、儚かった。まるで闇の中で見つけた最期の灯に取りすがっているようにもみえた。
「お願い・・・あと一分でいいから、そばにいて・・・」
その時、彼女はつぶやいた。独り言かもしれない、あまりに小さなその声は、すぐそばで嘶く雨脚にさらわれた。
あと一分。彼女はそういった。
僕は聞き返したかった、本当に、あと一分でいいのか? 僕を、ずっと必要とはしてくれないのか?
秋の夜はあまりに冷たく、長かった。静寂の中、僕は彼女の願いが変わることを祈っていた。
« 全国未亡人連合-画廊・花火- | メイン | 全国未亡人連合-画廊・冬の散歩道- »
全国未亡人連合-画廊・雨-
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.w-room.net/mt/mt-tb.cgi/49
2010年04月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最近のコメント
最近のエントリー
リンク
検索
Powered by
Movable Type 3.34
Movable Type 3.34