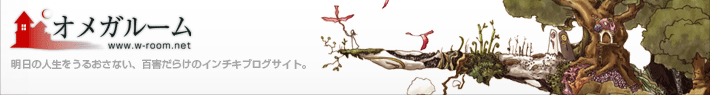僕はその日、早起きをした。
僕はその日、早起きをした。
別に早く起きる理由なんて無かった、ただ単に、目がさめ、それ以上眠りにつく必要が無かっただけだ。
ここは旧家の母屋だった、旅先で偶然知り合った女性の家に泊めてもらったのだ。
もちろん、旅先で偶然見ず知らずの男を泊めるような女性であるから、未亡人だった。
その未亡人の好意に計らい、この家で一泊させてもらった、ただ長居する気はなかった、別に居心地が悪いわけでも、何か嫌な事が合ったわけでもない、あてのない放浪の旅に「あて」を作るのを望まないだけだった。
僕はとりあえず顔を洗おうと、水場を探した、しかしここは母屋の為か水が出そうな場所はなかった。
そこで主屋の方に向かった。
古い建物である、昔ながらの日本家屋だったが、庭の剪定から壁や柱の修繕まで、全く文句のつけようの無い完全さがそこにはあった。それは、見ていてなかなか気持ちのよいものだった。ある種の完全さは、時に人を落ち着かせ、柔らかい安定へと導く、この家が建てられてどのくらいの日を見たのかはわからない、ただここにある全てが古い時間のまま、すべてを安定させ、変化を許さない完全さで覆われていることを、僕は理解した。そしてそれは、彼女を時として束縛しているのかもしれない、ぼんやりそんなことを考えた。
僕は台所と風呂場と思しき家屋の戸を見つけた。なぜそれが台所と風呂場と判断できたのか、理由は二つある。昔の家屋の作りは、木造建築は痛み易いので水周りは隣接させ一箇所の、しかも建物とは別棟で作られる場合が多かった(修繕する時便利だから)というのがひとつと、井戸が外にある場合、風呂場の水を張ったり多く水を使う炊事の時等は何度も水を汲む必要があったので、大体は水場の棟には勝手口がついているものであるというのが理由である。
勝手口の握りに手をあて、強く引いてみた、鍵はかかっていなかった。
あまり音を立てないように中にはいると、そこに未亡人がいた。
白襦袢をたくし上げ、長い髪を丁寧に漉いていた。
どうやら台所で髪を洗っているらしかった、そうか、昨日は夜遅かったからお風呂に入れなかったのか。
旧家の風呂だから、薪焚きのため、朝シャワーを浴びるなどという都会暮らしの女性のようなことは出来ない、そこで嗜みのために、台所で髪を洗っていたのだろう。
僕は、そんな光景を、なんだか昔なくした自分の記憶を題材にした活動写真を見るように、ぼうとみつめた。
ここの時間は、本当に止まっているんだ。
「? 何をそんなに真剣に見つめているの?」、彼女は不思議そうに僕を見た。
「あ、いや。なんだか、昔こんな光景を見たような気がするなあ、って」、僕は正直な感想を言った。
彼女はくすりと笑い、タオルで髪を拭きながら、
「それ、既視感っていうのよ」、と言った。
既視感、デジャブ、確かにそうかもしれない、僕ははるか昔、あるいはまだ生まれていない太古の時間の中で、こんな光景をみていたのかもしれない、それはあまりに安定し、穏やかで、僕の根幹と繋がっていた。
知りたい、この時間の中で、もっと色んなことを明らかにしたい、ふとそう思った。
「ねえ」、彼女が髪を丁寧に結上げている姿を見ながら言った、「もし良かったら、もう少しここに泊めてくれないか?」
彼女は答える代わりに、にっこりと微笑み、頷いた。
そして、まだ少し水気を含んだ髪をさらりとなびかせ、振り向いて言った、
「そうなるって、わかっていたの」。
デジャブ、僕と彼女の時間は、こうしてその始まりを告げた。
« 全国未亡人連合-画廊・辻斬り- | メイン | 全国未亡人連合-画廊・朝霧- »
全国未亡人連合-画廊・ある朝-
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.w-room.net/mt/mt-tb.cgi/52
2010年04月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最近のコメント
最近のエントリー
リンク
検索
Powered by
Movable Type 3.34
Movable Type 3.34