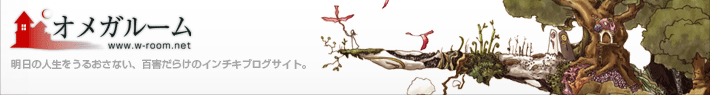秋田の山間にある村、白神の颪が視界を遮る。
東北の冬は厳しい、特にこのような農業を生業としている人たちは、一層自然の恐持てを知ることとなる。
霜は葉の熱を奪い、命は凍る、細い春への道を人も動物も作物も、肌を寄せ身を固め静に歩んでいくしかない。
そんな東北のこの地に僕が赴くことになったのは、全未連本部からの情報がきっかけだった。
冬は東京の街の熱を少しずつ冷まし、人々に落ち着いた営みを与え一つの年の終わりを告げる合図を送っていた。
そんな時期、僕の元に一通の手紙が届いた、和紙の封書の裏には住所も名前も無く、ただ綺麗な行書体で「全未連」とだけかかれていた。
未亡人研究家である僕は、この連合に属していた。
何か未亡人に関する有効な情報がある時お互いそれを交換し合う事ができる組織というのは、この国にはまだ少ない、全未連はそういう意味では貴重で有効な組織であった。
丁寧に封書を開け、手紙を取り出した。
手紙は白紙だった、しかし僕はピンときてライターで紙をあぶってみた。
案の定、文字が浮き出てきた、これは相当重要な情報らしい。
浮かび上がってきた手紙の文面、それは端的に、そして優雅な一文であった。
「とある農村の旧家で、未亡人が発生したらしい」、その情報を得るが速いか、僕はバックパックを担いで駆け出していた。
ただ、少し後悔はしていた、あの情報だけだと場所が判然としないのだ。未亡人に会えることを信じてずいぶん彷徨った、そして道に迷った。幾つかの森を越え、幾つかの山を越えた、それでも梢を出ることは無かった。バックの中の食料も底をつきかけていた、糒一握りと乾肉一切れ、これだけであとどのくらい生きていけるのだろう。木々の先でうっすら見える朝焼けの空を仰ぎ、溜め息をついた。
・・・・・・・・死ねない、こんなところで僕は死んではいけないんだ。僕が死ねば、僕の死を哀しむ誰かに辛い思いをさせていまう、それでは未亡人を残して死んでいった旦那と同じじゃないか。
そんなこと、許されるはずが無い、僕は、未亡人を見つけなければいけない、そして、彼女を末永く幸せにする必要があるんだ。
そのとき、僕の視界に、一人の女性の姿が現れた。朝霧の向こうにあるその姿は、冬枯れを耐え凌ぐ百合根のように見えた。
僕が近づくと彼女ははっとした表情でこちらを顧みた、目にはうろたえと訝しさの色が見え隠れしていた。
当然である、突然山奥から見たこともない男が出てきたのである、しかも、自分では分からないが何週間も山を彷徨っていたのである、ひどい顔になっているはずだ。
僕はまず彼女を安堵させてあげるために、バッグからカメラを取り出し、説明した、
「僕はフリーのカメラマンをやっているものですが、白神で撮影をしている途中道に迷ってしまったんです」。
それを聞き、彼女は幾分安堵したようで、こわばった表情を緩めた。
「それは大変でしたね、この近くに私の住んでる村があります、よろしければお立ち寄りください」
美人・・・・、山・・・・、村・・・・、僕はぴんときた、彼女が未亡人だ。
高鳴る胸を抑え、落ち着いた口調で聞いてみた、
「そうしていただけると大変助かります。ところでこんな朝早く、何をなさっていたのですか?」
彼女はそれを聞き、すこし顔色を曇らせた。答えるのに躊躇しているようにも見えた。
郭公の鳴き声が聞こえてきた、朝霧の梢に澄んだ声色が響いた。
朝はその静寂を森に横たえ、霧の息吹きに白い冷たさを与えていた。
それは永遠に覚めない夢のようでもあり、またたゆたう古い時の流れのようでもあった。
そして、その朝と同質の何かを彼女が持っていることを、僕は気がついていた。
どのくらい時間が立っただろう、沈黙をうめる彼女の言葉は意外なものだった。
「無駄なことをしていました」
僕は良く分からなかった、無駄なこと、こんな寒い朝に早く起き、やることに無駄なことなんてあるのだろうか?
「無駄なことですか?」
「はい、無駄なことです」、そう答え霧混じる空気を大きく吸った後僕の目を見て言った、「お百度まいりです」。
嗚呼、やはりこの人は未亡人だった、僕は確信した。
そしてそのお百度まいりが、死んだ旦那さんに向けられた、何らかの想いからきていることも理解した。
彼女は、それを無駄な行為と自覚している、それでも止める事の出来ない足と思慕に体を任せ、早朝の「無駄なこと」を欠かさず行っているのだろう。
複雑な思いがした、どう言葉をかけてあげればいいか迷った、そしてどんな言葉も彼女を救えないことも知っていた、今のところは。
そんな僕の迷いを知ってか知らでか、彼女は山を下りる道を歩き出した、僕はそれにならった。
段々と視界が広がっていった、森から抜け出し、遠くに村が見えたあたりで彼女はふと足を止めて、こちらを見て言った、
「忘れられない想いって、あってもよいのでしょうか?」
もちろん、僕はそう言いかけて口をつぐんだ、それは彼女を苦しめている根幹のように思えた、忘れられない想い、それほど深い感情に立ち入ることを許されるのに、人はどれだけ相手を想い慕わなければならないのだろう、その長い時間を、これから始まるであろう時間を思うと、僕の体は朝霧ではない何か別の寒さを覚えた。
僕は答える代わりに、彼女の手を小さく握った、凍結しそうな、冷たい指先だった。
「想いは、温かいから意味があるんです」、それが今の僕にできる、最良の答えだった、熱を与えられない相手への想いに、何の意味があるのだろう?
彼女は目を閉じ、少し口元を緩ませた、
「そうですね。貴方の手は、とても、暖かい」
こうして、僕のこの村での生活は始まった。
« 全国未亡人連合-画廊・ある朝- | メイン | 全国未亡人連合-画廊・感情の 起きたる荒野の 風の果て- »
全国未亡人連合-画廊・朝霧-
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.w-room.net/mt/mt-tb.cgi/53
2010年04月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
最近のコメント
最近のエントリー
リンク
検索
Powered by
Movable Type 3.34
Movable Type 3.34