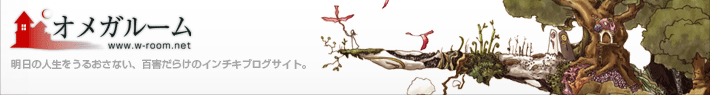「夢を見ていました」
緑映える夏の森を、彼女は歩いた。
空を仰げば、柔らかな陽光が枝葉の間隙を縫うようにこぼれている。
大地の褥を這うように、湿り気を帯びた風が、身体を覆う皮膚をなでた。
熱く、そして香るような夏の午後だった。
「夢を見ていたんです」
彼女はもう一度、つぶやいた。
言葉は森の梢を小さく揺らし、静寂と溶け合い、消えた。
*
森の中にひっそりと広がるその墓地で、彼女とであったのはほんの偶然だった。
僕は旅をしていた、薬の行商をする一族に生まれ、その運命と多くの命を救う妙薬を背負い、全国を回っていた。
薬師、古くはそういわれる我々一門も、現代では薬剤師の免許を持っていない不法の薬物売買組織とにらまれている、だからこうして社会の闇に身を潜め、その血に従い必要としている人に秘薬を売っている。
この夏、青森の奥入瀬で古い旅館を営む18代目主人に頼まれ、長女の憑き物を払う妙薬を屈指し怨霊を退治した後、奥州街道を南下し、日光を目指していた。
しかしその道中、山賊(チーマー)に襲われたアジト(廃ビル)に連れて行かれてしまった。
彼らの食事にこっそり仕込んだ禁薬(トリカブト)で難を逃れたが、街道から大きくそれてしまった。
僕は旅で培った方向感覚を屈指し、南と思う方向を目指し、歩き始めた。
そしてたどり着いたのが、この北海道の片隅にある森の、墓地だった。
墓地にも衰退があることを、僕はそこで初めて知った。
その墓地にある墓はみなコケがむし、庭園はうっそうとした雑草に覆われ、卒塔婆から生えた小さな菌類はその宿主を朽ち果てさせていた。
墓場に死がある、不思議な感じだった、「墓の死」はむしろそこにある死の予感を軽減し、光景としてそのレーゾンディーティルを昇華させていた。
それはあまりに主体の無い、完成された客体だった。
「死の退廃」、悪くない、その意味では死というのは厳然たる「生」の延長にあるものかもしれない。
石垣りんの詩を思い出した、「死」は「生」のために用意されたもの――。
命を救う薬師としての自分の存在価値が、すこしだけ煙たく感じた。
その墓場をぼんやりと眺めながら、そんなことを考えていた。
すると、向こうのほうで、誰かが薄汚れた墓に向かって手を合わせている女性の姿に気がついた、紫の丹前が緑の森と溶け合い、気が付かなかったのだ。
こんな墓地でも、まだ機能しているのか、僕は小さな驚きと、わずかな落胆を覚えた。
すると、遠くで見える女性の像が緩やかに倒れるのが見えた。
慌てて駆け寄った、女性は貧血で倒れてていた。
貧血、というのは「黒餓鬼」という低階層の悪霊が起こす病である、僕は薬筒の中から「黒餓鬼」を払う効果のある、「場婦亜鈴」という妙薬を取り出し女性に飲ませた。
すると女性の顔色はみるみる回復していった。
「あ・・・」
「お気づきですか? もう大丈夫です」
僕は彼女を抱き起こした。
「すいません、私、脚気が酷くて時々、意識が朦朧とする時があるんです・・・」
(ちなみに、「場婦亜鈴」は脚気にも効く)
「助けていただいて、ありがとうございます。あの・・・薬師の方ですか?」
女性の言葉に驚いた、なぜ僕を薬師と見破ったのだろうか? まさか敵(日本医学協会)?
僕は懐のトリカブトを握り、慎重にたずねた、
「なぜそれがわかったのですか?」
すると女性はにっこりと笑った、
「未亡人は勘が鋭いものよ」
僕は二重に驚いた、未亡人というにはあまりに女性は若く見えた。
年のころ、20台半ばといったところだろうか、あるいは年よりずいぶん若く見えるだけかもしれない、それだけ彼女ははかなく、頼りなげに見えた。
しかしこんな日に、丹前で墓場に来るなんて、未亡人以外ありえなかった。
なるほど、未亡人ならば納得だ、ほっと胸をなでおろした。
未亡人は万能人間である、僕の仕事くらい顔を見ればすぐにわかって当然である。
「旦那さんの、墓ですか?」
彼女が先刻まで手を合わせていたであろう墓を見ながら、そう言った。
「いいえ、違います」
彼女は答えた、本当に僕を驚かせてくれる女性である。
「旦那さんでもない人の墓参りに来ていたのですか?」
彼女は目の前の墓を見た、
「私の夫に、墓はないんです。いえ、作れないんです」
そう言い、僕を見つめた、澄んだ、あまりににごりの無い目だった、
「夫は、薬師でしたから」
なるほど、僕はやっと理解した。
薬師は時代の陰で生きる一族、その生も死も社会的に容認されたものではないのである。
出生届も出されなければ、死亡届もない、だから墓を作る意味もない、のたれ死んだところが墓なのだ。
「夫は、敵に囲まれた時、禁薬を飲んで、立派に果てたと聞いております」
彼女は空を見上げた、そこにある一片の雲に何らかの思いをのせているように見えた。
「せめて、誰からも祈られることの無い骸が眠る墓を借りて、亡き夫への哀悼を致したく、ここに足を運んでるんです」
そう、薬師はたとえ闇に生きる種族だとしても、それを待つ人はいるのである、誰からも許されることの無い「生」と「死」を認めてくれる、待人がいる、彼女はそんな悲しい、薬師の妻なのである。
僕はしゃがみ、その墓に向かい手を合わせた、いずことも知らぬ骸と魂に祈りを込めた。
僕に習い、彼女ももう一度、その墓に手を合わせた、朽ち果てた墓場の、死んだ墓向かって。
お礼に、うちでお茶でも飲んでいってください。
彼女の誘いを断る理由もなかった、そうして僕らは森の道へと引き返した。
*
「夢を見ていたんです」
彼女の言葉は、蒸した空気でさえその領域を侵すことの出来ない、凍りついた表土から沸いた霜のように、悲しい透徹さに満ちていた。
「夫と、誰からも祝福されるような、ささやかな毎日。誰からも悲しまれるその死、そういった、あたりまえの生活を、夢見ていたんです」。
それは薬師に恋し、ひとつになった女性の、悲しい夢だった。
「でも、旦那さんのことを、愛していたわけですよね。お墓に、通いつづけているくらいだから」
僕は歩きながら彼女に尋ねた、それは僕自身のための質問でもあった。
たとえ闇に生きる人間であっても、誰かからは愛され、必要とされ、望まれている、誰かに望まれているかぎり、僕ら一門は人としてその生を幸福なものとしてまっとうできる、そう信じたかった。
しかし彼女の答えは、違った、
「わからないの。それが、本当の愛だったのか、もう、わからないの」。
彼女は歩を止めた、一歩後ろを歩く僕を振り返り見ることも無く、地面に向かって吐くようにそう言った。
先ほどまでの穏やかで、静かだった彼女の背中が小刻みに震えていた。
「ねえ、私達、誰からも祝福されなかったのよ。一緒になる前から、なった時も、なった後も、誰一人として私達の関係を認めてくれる人はいなかった。
誰からも、夫が死んだことに対して、慰めや励ましを受けなかったわ。
あれだけ人を助け、人を救うために北から南まで休むことなく歩きつづけ、死んだのよ。それなのに・・・。
一緒に暮らした時間だって、ほとんどなかった。
もちろん、あの人のことは好きでした、好きだから、一緒になったの。
でも誰からも認知されない想いだったのよ。誰一人として・・・」。
いつのまにか、彼女は泣いていた、たまっていた感情を吐露するかのように、激しい言葉を口にした。
「ねえ、それは、そんなのは、愛と呼べるの? そんな間柄を生むのが、愛なのですか?」
僕は何も答えられなかった。
彼女が、夢と言った意味が、少し理解できた。
それはリアリティのない空想だった。
薬師を夫とした瞬間、捨てられてしまった日常が、彼女の夢だった。
僕の一族は、そんな悲しい犠牲の上で、その血を引き継いできた。
そしていずれ、僕も、そんな悲劇の輪廻の中で、繰り返される犠牲の螺旋でその血を延命させるのだろうか。
*
僕は空を見上げた、そこに夏はあった。
夏は不完全な熱さを森に与え、僕らが生きる空間を侵すことなくその蒸気を空へと返していた。
自分の血をのろったことはない、ただ、その陰惨な流れに否定しようの無いむなしさを感じた。
彼女のすすり泣く声は、季節の間隙に吸い込まれ、やがては消えていくのだろう、それは足跡を残さない僕らのように、ただ予感だけを残しながら、霧散する。
ただ、それだけなんだ。
その時の僕に知る由はなかった、
彼女は、僕自身が生み出した、母の亡霊であることを。
僕がいつのまにか感じていた虚ろな予感が、母の霊となり、僕に語りかけてきたことを。
僕の25度目の夏は、僕と僕自身の血への疑問との旅になった――。